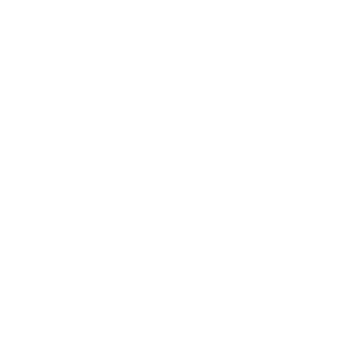文体私論
- 2025年2月4日
- Monthly Essay
“身体”が人それぞれ違うように“文体”も人それぞれ個性があって面白い。そこで『自分の文体の個性って何だろう?』について論じてみたい。あくまで連載や書籍のように専門的なことを書く時の文体を想定してみる。
このエッセイもそうだが、“だ・である調”を基本としている。たま~に“です・ます調”でお願いしますという原稿依頼を受けて、書いているうちにいつの間にか“だ・である調”に替わっていて「アカン、アカン」と言いながら修正している。“だ・である調”は教科書や論文などで採用されるが、教科書が私の文体と違うのは「主語が無い」ところだ。広く一般化したような内容を書くときに“私は”なんて主語はじゃまなのだ。読者にしても教科書で勉強するときに、筆者個人の考えを求めないだろう。コラムもそんなニュアンスがある。でも私が書く内容はどんなに硬い内容であっても“私”というバイアスがかかっているので、「この文章の責任は私が負います」という意味も込めて主語を入れる。参考文献をつければある程度“根拠の所在”は示せるだろうが、“責任の所在”も必要だと思っている。
教科書や論文では日本語というルールにきっちり従っているので、正しく読者に伝わるように文章が工夫されている。間違って伝わってしまったら大変という“責任感”は強いのだ。それに対して私の文体ではスピード感とリズム感を考えるので、正しく伝わらない可能性が出てくる。なので当然のことながら追加説明のやたら多い校正原稿が返ってくる。編集者が読者の誤読を心配して、丁寧に文章を正してくれているのだ。でもほとんど無視して編集者の心配を煽っている。追加説明付き文章はまどろっこしくなっていて、スピード感が無くなるから。私はできれば「一気に読んでしまいました!」というような感想が欲しいのだ。むしろ誤読の可能性を残しているほうが面白いと思っているくらいだ。
文章のスピード感が連載の回ごとに変わらないほうがよい。それがバラバラだと本になったときに統一感がなくなる。共著の本がたくさん出ているが、文体が違うだけでなく、スピード感もバラバラなのでどうしても“寄せ集め感”が前面にでてしまう。せっかく一人で書くのであれば、文体だけでなくスピード感も統一したい。それを実現する私のやり方は、、、連載原稿を一気に最後まで書いてしまうということだ。
こうやって自分の文体を改めて俯瞰してみると、教科書的な“だ・である調”であるにもかかわらず、“私”が出てくる“エッセイ調”で、スピード感を意識したものであるようだ。体力が落ちてきてどれだけスピード感を維持できるかわからないが、とりあえずこの原稿は40分ほどで書き上げた。